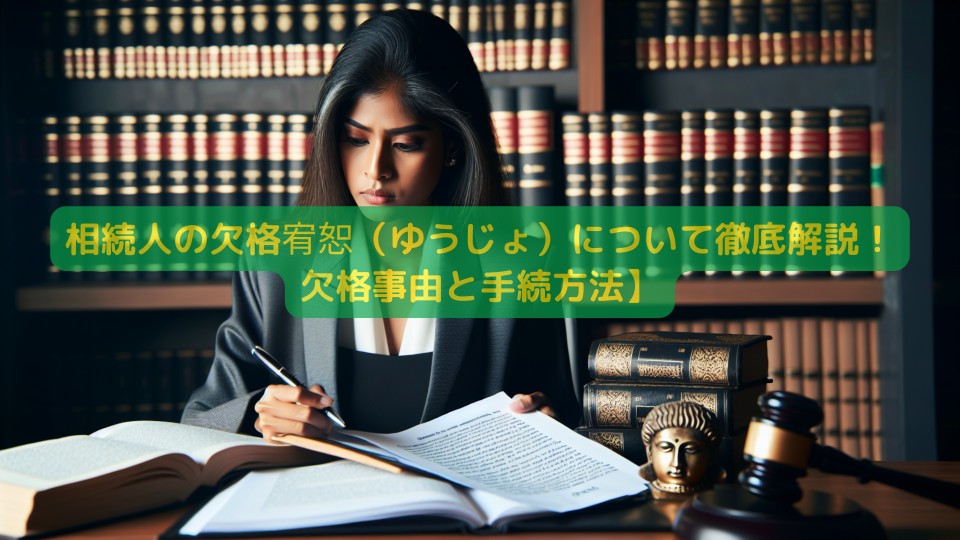
こんにちは、宅地建物取引士の刈田です。
不動産を扱うことも多いこの仕事、相続の話題は切っても切り離せません。
中でも「相続人の欠格」って、皆さんご存知ですか?
遺産を受け継ぐはずの相続人が、 行方不明 だったり、遺言書を偽造 したり…そんな場合に発生する可能性があるんです!
「え、じゃあ財産はどうなるの?」「そんな事態を防ぐ方法はあるの?」
今回は、そんな相続人の欠格と、そこから発生する「宥恕」という制度について、わかりやすく解説していきます。
相続人の欠格宥恕(ゆうじょ)についての基本知識
相続が発生すると、故人の遺産は相続人に引き継がれます。しかし、民法では、一定の事由がある場合、相続人としての資格を喪失すると定められています。これを「相続欠格」といいます。例えば、故人を殺害したり、遺言書を偽造したりした場合などが該当します。
一方、「相続人の欠格宥恕」とは、たとえ相続欠格事由に該当する場合でも、家庭裁判所の審判によって、相続人としての資格を回復できる制度です。これは、相続欠格が厳格すぎる場合に、家族関係の情実や当事者間の衡平を考慮して認められることがあります。宥恕とは(スル)寛大な心で罪を許すこと。
欠格宥恕の申立ては、相続開始を知ってから6ヶ月以内に行う必要があり、審理は家庭裁判所で行われます。審判では、欠格事由の有無や当事者間の関係などが考慮されます。
相続欠格とは何か
相続欠格とは、民法で定められた一定の事由がある場合に、相続人としての資格を失う制度のことです。
例えば、故意に被相続人や先順位の相続人を殺害した場合や、被相続人の遺言書を偽造・破棄した場合などが該当します。
たとえ、本来であれば相続人となるべき立場であったとしても、これらの行為によって被相続人や他の相続人に対して重大な背信行為を働いたと判断されれば、相続人としての資格を剥奪されてしまうのです。
相続欠格は、相続人の地位を剥奪する非常に重い制度であるため、安易に適用されることはありません。
相続欠格と相続廃除の違い
民法は、一定の場合に相続人を相続から排除する制度として、「相続欠格」と「相続廃除」を定めています。
「相続欠格」とは、例えば、被相続人を殺害するなど、著しく非道な行為を行った者について、その者を相続人から排除する制度です(民法891条)。家庭裁判所の審判は不要で、最初から相続人となる資格がありません。
他方、「相続廃除」は、例えば、被相続人を虐待するなど、著しく非道な行為を行った者について、被相続人が遺言によって、その者を相続人から排除できる制度です(民法892条)。家庭裁判所の審判が必要です。
このように、相続欠格と相続廃除は、対象となる行為や、家庭裁判所の審判が必要かなどの点で異なります。
中古一戸建てをお探しですか?
『東京中古一戸建てナビ』では、非公開物件を含む豊富な物件情報をご案内しています。
無料会員登録はこちら
相続欠格の具体的な事由
民法では、一定の事情がある場合に相続人としての資格を失う「相続欠格」について定めています。 相続欠格の事由には、例えば、被相続人を殺害したり、遺言書を偽造したりした場合などが挙げられます。 また、被相続人のために遺言書を作成することを妨害したり、すでに作成された遺言書を破棄したりした場合も含まれます。これらの行為は、相続制度の根幹を揺るがす重大な行為として、相続欠格事由とされています。しかし、このような場合でも、常に相続権を失うわけではありません。家庭裁判所の審判によって、相続権を回復できる可能性があります。これを「相続欠格の宥恕」といいます。
相続欠格になる5つのケース
民法は、一定の事実がある場合に、相続人を相続から排除する制度である相続欠格を定めています。 これには、被相続人を虐待したり、遺言を偽造したりするなど、 相続人としての資格を欠く重大な行為が挙げられます。 具体的には、(1)故意に被相続人などを殺害した場合(2)被相続人の殺害を教唆または幇助した場合(3)被相続人が作成した遺言書を偽造したり、破棄したり隠匿した場合(4)被相続人を脅迫して遺言を書かせた場合(5) 相続について証言や診断書を偽造した場合の5つが該当します。 しかし、これらの行為があったとしても、家庭裁判所の許可を得ることで相続人となることができます。 これを相続欠格の宥恕といいます。
被相続人や同順位以上の相続人を故意に死亡させた場合
相続においては、民法で定められた相続順位や相続分に従って、遺産の分配が行われます。しかし、中には、被相続人や同順位の相続人を故意に殺害したり、遺言書を偽造したりするなど、悪質な行為によって相続財産を取得しようとする者がいます。このような行為は、法律によって厳しく罰せられます。
民法第891条では、被相続人、先順位もしくは同順位の相続人を故意に殺害した者は、相続人となる資格を失うと規定されています。これが「相続人の欠格」と呼ばれるものです。たとえ、殺人罪で無罪となっても、民事裁判で殺害の事実が認められれば、相続欠格事由に該当すると判断されます。
ただし、このような場合でも、家庭裁判所の審判によって、相続人の資格を回復できる場合があります。これを「相続人の欠格の宥恕」といいます。
被相続人が殺害されたことを知りながら告発・告訴しなかった場合
相続開始後、被相続人が殺害されていたことが判明した場合、大きな衝撃を受けるでしょう。このような場合、たとえ殺人罪で確定判決を受けていなくても、相続人の欠格事由に該当します(民法891条)。これは、自身の不利益になる事実を隠蔽する可能性を考慮しての規定です。
しかし、民法は、一定の条件のもと、家庭裁判所の審判によって、この欠格事由を解消できる制度を設けています(相続人の欠格宥恕、民法892条)。宥恕が認められるためには、相続人が殺害に関与していないこと、または殺害の原因についてやむを得ない事情があることなどを家庭裁判所に申し立て、認められる必要があります。
確実な遺産相続のためにも、専門家である弁護士や司法書士に相談し、適切な対応を取りましょう。
詐欺・脅迫によって被相続人の遺言を妨げた場合
相続人の欠格事由に該当する場合でも、いつも相続権を失うとは限りません。例えば、詐欺や脅迫によって被相続人に遺言を書かせなかったり、すでに作成された遺言を破棄させたり隠匿した場合、たとえそれが事実だとしても、家庭裁判所に「宥恕」の申し立てを行い、認められることで相続人としての地位を取り戻せる可能性があります。これは、相続人の排除による相続財産の偏りや、残された家族関係への悪影響を考慮して設けられた制度です。ただし、宥恕が認められるには、 相続人としての資質があると認められることなどが条件となります。
詐欺・脅迫によって被相続人に遺言をさせたり撤回・変更させた場合
相続人の欠格事由の1つに、「詐欺や脅迫によって、被相続人に遺言を書かせたり、撤回・変更させた場合」があります。このような行為は、被相続人の意思を不当に歪めるものであり、相続人の資格を剥奪するに値する重大な不正行為とみなされます。
ただし、民法には「相続人の欠格宥恕」という制度があります。これは、たとえ欠格事由に該当する場合でも、一定の条件を満たせば、家庭裁判所の許可を得て、相続人としての資格を回復できるというものです。具体的には、他の相続人全員の同意を得るなど、一定の要件を満たす必要があります。
この制度は、相続人の立場を一方的に奪うのではなく、反省の余地を与え、家族関係の修復を促すことを目的としています。
被相続人の遺言書を偽造・変造・破棄・隠蔽した場合
被相続人の遺言書を偽造したり、自分に有利なように書き換えたり、破棄・隠蔽する行為は、相続人の欠格事由にあたります。たとえ故人のために尽くしてきた相続人であっても、このような行為は法律で厳しく罰せられます。刑法では、5年以下の懲役とされています。
ただし、偽造・変造・破棄・隠蔽した相続人が、他の相続人全員の同意を得られれば、家庭裁判所の審判により、相続人としての資格を回復できます。これを「相続人の欠格の宥恕」といいます。
遺言書に関するトラブルは、感情的な対立を生みやすく、解決が困難になりがちです。専門家である弁護士などの協力を得ながら、冷静に解決を目指しましょう。
相続欠格の影響とその対処法
相続人が廃除されると相続権を失いますが、場合によっては家庭裁判所に申し立てて、欠格の効果を消滅させることができます。これを「相続欠格の宥恕」といいます。例えば、遺言書で財産をもらえないことになっていた相続人が、被相続人から生前贈与を受け、他の相続人と均衡を図っていたケースなどが考えられます。宥恕が認められるかどうかは、家庭裁判所が具体的な事情を考慮して判断しますので、専門家である弁護士や司法書士に相談することをおすすめします。
相続欠格になるとどうなるか
民法では、本来相続人となるべき人でも、一定の事由がある場合には、相続権を失うと定められています。これを「相続欠格」といいます。 相続欠格が認められると、その人は、初めから相続人ではなかったものとみなされ、相続財産を取得する権利はなくなります。たとえ、遺言で財産の分与が指定されていても、無効となります。相続欠格の事由としては、被相続人に対する虐待や遺言書の偽造など、重大なものが挙げられます。ただし、被相続人が生前に許した場合は、この限りではありません。これを「宥恕」といいます。
相続権の喪失と遺贈の受け取り不可
相続欠格によって相続権を失ったとしても、被相続人の宥恕があれば、相続人としての地位を取り戻せる可能性があります。これが「相続欠格の宥恕」と呼ばれる制度です。 たとえば、被相続人を虐待したために相続欠格となった人が、その後、被相続人と和解し、深い反省の情を示した場合などが考えられます。 宥恕は遺言によって行うことも、口頭でも有効とされています。ただし、後に問題となることを防ぐため、明確な証拠を残しておくことが重要です。
遺留分の権利も失う
相続人の欠格事由に該当する場合でも、被相続人が生前に許していた場合は、相続人としての資格を回復できます。これを「宥恕」といいます。遺言で「相続させない」と明記されていない場合でも、家庭裁判所で「推定宥恕」が認められる可能性もゼロではありません。ただし、一度は相続権を失っていることを考えると、確実に相続するためには、改めて遺言書を作成してもらうなど、対策が必要です。遺留分についても同様で、本来は認められる権利も、欠格によって失う可能性があることを覚えておきましょう。
相続欠格の確定と手続き
民法は、故意に被相続人などを殺害したり、遺言を偽造したりした相続人について、相続の資格を失うと定めています。これを「相続欠格」といいます。
相続欠格は、家庭裁判所の審判によって決まります。ただし、被相続人が生前に、すでにその事実を知りながら許していた場合は、相続欠格の対象から外れることがあります。これを「宥恕」といいます。
宥恕の事実を主張するには、家庭裁判所に「相続人の欠格の不存在」の申し立てをしなければなりません。この申し立てには、被相続人が生前に許していたことを証明する資料が必要となります。具体的には、遺言書や、被相続人とやり取りした手紙などが挙げられます。
相続欠格の確定方法
相続欠格が確定すると、たとえ遺言で財産を渡すと指定されていても、相続人になることはできません。では、どのようにして欠格が確定するのでしょうか?
家庭裁判所で審判が確定すれば、その者は相続欠格者となります。ただし、相続開始後、家庭裁判所の許可を得れば、相続人となることも可能です。これを「相続人の欠格の宥恕」といいます。
相続人の欠格は、ご家族間の問題であり、非常にデリケートな問題です。専門家である弁護士や司法書士に相談し、適切な対応をすることが重要になります。
相続欠格は手続きなしで確定する
民法では、一定の場合に相続人となる資格を失うことを「相続欠格」と定めています。例えば、被相続人を殺害したり、遺言を偽造した場合などが該当します。
相続欠格は、家庭裁判所の審判によって決まるわけではありません。相続欠格事由に該当する事実があれば、その時点で自動的に相続人となる資格を失います。
ただし、被相続人が生前に許していた場合など、一定の事由があれば、家庭裁判所の審判により相続権を得る可能性があります。これを「相続欠格の宥恕」といいます。
相続欠格者が反論する場合の対応
民法で定められた相続欠格事由に該当する場合でも、家庭裁判所に申し立てて、相続欠格者の欠格権を消滅させることができます。これを「相続欠格者の宥恕」といいます。申し立ては、相続が開始したことを知ってから6ヶ月以内に行う必要があります。家庭裁判所は、相続人の状況や被相続人との関係などを考慮して、宥恕を認めるかどうかを判断します。過去の判例では、暴力団員との婚姻や、婚姻期間が7日間の婚姻などが、宥恕が認められなかった例として挙げられます。一方で、長年にわたる音信不通や、被相続人に対する虐待などが、宥恕が認められた例として挙げられます。
相続登記の際に相続欠格の証明が必要な場合
相続人が被相続人に対して虐待や遺言書の偽造などを行った場合、家庭裁判所に 相続欠格 を申し立てられる可能性があります。相続欠格が認められると、その相続人は相続権を失います。
ただし、被相続人が生前に許していた場合などは、家庭裁判所で 相続欠格の宥恕 が認められる可能性があります。
相続欠格の事由に該当するかどうか、宥恕が認められるかどうかは、過去の判例や具体的な事情を踏まえて判断されます。専門家である弁護士や司法書士に相談することをおすすめします。
施工現場からのアドバイス
中古一戸建ての購入やリフォームを検討されている方に、私たちが現場で培ってきた経験からアドバイスをお伝えします。
物件選びでは「建物の構造」と「土地の条件」の両方を確認することが重要です。見た目の綺麗さだけでなく、基礎や構造躯体の状態、接道条件、用途地域などを必ずチェックしてください。これらは将来の資産価値にも大きく影響します。
不安な点があれば、専門家に相談することをおすすめします。私たち「東京中古一戸建てナビ」では、宅地建物取引士による物件調査を無料で実施しています。
相続人の資格回復と宥恕(ゆうじょ)の可能性
相続欠格となった人が相続人になれるケースとして、「資格回復」と「宥恕」があります。資格回復は、禁錮以上の刑の執行が終わったり、刑の執行猶予期間を経過したりした場合に、家庭裁判所の許可を得て相続人としての資格を回復する手続きです。一方、宥恕は、被相続人から虐待を受けたり、著しく侮辱されたりした場合に、相続欠格の理由があったとしても、他の相続人の請求により、家庭裁判所の審判を経て相続人になれる可能性がある制度です。いずれも、複雑な事情や手続きが必要となるため、弁護士等の専門家へ相談することをおすすめします。
相続人資格の回復は可能か
相続人の欠格事由に該当する場合、相続権を失うことになりますが、場合によっては家庭裁判所の許可を得て、相続人としての資格を回復できる場合があります。これを「相続人の欠格の宥恕」といいます。例えば、被相続人を虐待した相続人が、その後真摯に反省し、他の相続人と和解した場合などが考えられます。家庭裁判所は、被相続人の意思、相続人の状況などを考慮して、宥恕を認めるかどうか判断します。宥恕が認められると、最初から欠格していなかったものとみなされ、相続権を取得できます。ただし、宥恕は自動的に認められるわけではなく、適切な手続きと、認められるだけの十分な理由が必要となります。
宥恕(ゆうじょ)の余地について
遺産分割協議で揉める原因の一つに、被相続人に対する虐待や侮辱などがあります。このような行為をした相続人は、たとえ民法で定められた相続人であっても、家庭裁判所で相続欠格の申し立てをされてしまう可能性があります。相続欠格事由に該当する場合でも、被相続人が生前に許していた、あるいは他の相続人が容認していたなどの場合には、家庭裁判所の判断によって、相続権が認められることがあります。これを「宥恕」といいます。宥恕が認められるか否かは、具体的な事情を総合的に判断されます。過去の判例や事案を参考にしながら、専門家である弁護士や司法書士に相談することをおすすめします。
相続欠格に関するよくある質問
相続欠格というと、ほとんどの方が「ありえない!」と感じるのではないでしょうか。しかし、ニュースなどで「親族間で遺産を巡ってトラブルに…」という話を見聞きする機会は少なくありませんよね。実は、このようなケースで相続欠格や、それを無効にする「宥恕」が関係してくることがあるのです。
例えば、遺言書を偽造したり、他の相続人に危害を加えたりする行為は、相続欠格事由に該当します。つまり、本来受け取れるはずの遺産を受け取れなくなってしまう可能性があるのです。
一方で、宥恕は、家庭裁判所の審判によって、これらの行為を許し、相続権を回復させる制度です。
相続は、感情的な問題も絡み合い、複雑になりがちです。専門家である私たちにご相談いただければ、「円満な相続」を実現するためのお手伝いをさせていただきます。
相続欠格になったら戸籍謄本に記載されるか
相続欠格が認められると、家庭裁判所の審判を経て、欠格者は相続人ではなくなります。ただし、戸籍にその事実が直接記載されることはありません。相続欠格はあくまでも相続資格の不存在に関する事項であり、戸籍は氏名や生年月日、婚姻関係などを記録するものです。
相続関係を明確にするためには、相続欠格審判書の他に、被相続人の出生から死亡までの連続した戸籍謄本や、相続人全員の戸籍謄本が必要となるケースが多いでしょう。 相続手続きは複雑になりがちなので、専門家へ相談することをおすすめします。
相続欠格者であることを確認する方法
相続人が誰か、遺産は誰が相続するのかは、民法で定められています。しかし、民法で定められた相続人であっても、一定の事由がある場合には、相続権を失うことがあります。これを「相続欠格」といいます。
例えば、故意に被相続人(亡くなった方)を殺害したり、遺言書を偽造したりした場合などが該当します。
相続欠格者かどうかを確認するには、家庭裁判所に申立てを行い、審判を請求します。審判で相続欠格者であると認められると、初めから相続人ではなかったものとみなされます。
ただし、相続欠格者であっても、被相続人が生前に「許す」という意思表示をしていれば、相続権を失わずに済みます。これを「相続欠格の宥恕」といいます。
相続欠格になった場合、他の親族の相続でも欠格になるか
相続欠格になった人が、その後、別の親族の相続でも欠格になるのかどうか、気になりますよね。結論から言うと、一度相続欠格になると、その相続に限って欠格となるため、他の相続には影響しません。
例えば、兄Aさんが父親の遺産を隠匿したため、父親の相続において相続欠格になったとします。その後、叔父Bさんが亡くなった場合、Aさんは叔父Bさんの甥であるため、本来であれば相続人になる可能性があります。この場合、Aさんは父親の相続では欠格していますが、叔父Bさんの相続では欠格になりません。
ただし、叔父Bさんの相続においても、Aさんが新たに遺言書を偽造するなど、相続欠格事由に該当する行為をした場合には、叔父Bさんの相続においても欠格となる可能性があります。
代襲相続と欠格の関係
相続人の欠格事由に該当した場合でも、被相続人が「許す」という意思表示をすれば、相続人としての地位を失わずに済みます。これを「欠格の宥恕」といいます。
例えば、兄が父親を殺害した場合、刑に処されると同時に民法で定められた相続欠格事由に該当し、父親の遺産を相続することができなくなります。
しかし、父親が遺言書で「殺害という行為は許さないが、息子である兄には相続させたい」という意思を示していた場合、兄は相続人としての資格を回復し、遺産を相続することができます。
欠格の宥恕は、遺言書や、口頭で伝えられた内容を家庭裁判所が認めることで有効となります。代襲相続とは、本来相続するはずであった者が、被相続人よりも先に亡くなったり、相続欠格者になった場合に、その子や孫が代わって相続人になる制度です。
相続欠格になった場合の代襲相続
相続欠格となった者がいても、必ずしもその子や孫までが相続できないわけではありません。民法には「代襲相続」という制度があり、欠格となった者の代わりに、その直系卑属(子や孫など)が相続人となることができます。
例えば、Aさんが亡くなり、本来は相続人となるはずの息子Bさんが、遺言書を偽造したため相続欠格になったとします。この場合、Bさんの子であるCさんが、代襲相続人としてAさんの財産を相続できます。
ただし、代襲相続は、あくまで本来の相続人が欠格となった場合にのみ認められる制度です。相続放棄や廃除によって相続権を失った者の代わりに、その子や孫が相続人になることはできません。
孫への相続の影響
相続において、孫への影響が気になるケースの一つに「相続人の欠格」があります。これは、民法で定められた一定の行為(例えば、故意に被相続人を殺害した場合など)を理由に、相続権を失う制度です。もし、あなたの子供が欠格者となった場合、その子供は相続できませんが、代襲相続という制度により、あなたの孫が相続人となることが可能です。
ただし、欠格事由があっても、家庭裁判所の審判により、相続権を回復できる「宥恕」という制度があります。宥恕が認められるかどうかは、具体的な事情によって判断されますが、孫への影響も考慮要素の一つとなるでしょう。
相続手続きのサポート情報
相続で揉めたくない!とお考えのあなたへ。遺産分割協議がまとまらない、音信不通の相続人がいる…様々なケースが考えられますよね。中でも、相続人としての資格を失う「相続欠格」をご存知ですか?例えば、故意に被相続人を死亡させた場合などが当てはまります。ただし、「相続欠格者の生活保障」という観点から、家庭裁判所の許可があれば、相続できる場合もあるんです。それが「相続欠格の宥恕」です。専門家も交え、状況を整理し、納得のいく解決を目指しましょう。
相続手続きの専門家によるサポート
相続手続きは、ただでさえ複雑で、精神的にも負担が大きいものです。もし、相続人の欠格事由に該当する可能性がある場合は、なおさら手続きが難航することが予想されます。
相続人の欠格事由とは、例えば、被相続人を虐待したり、遺言書を偽造したりした場合に、相続権を失うというものです。
ただし、このような場合でも、家庭裁判所に申し立てを行い、許可を得ることができれば、相続人となることができます。これを「相続人の欠格宥恕」といいます。
手続きの複雑さや専門的な知識を要することから、弁護士や司法書士などの専門家に相談することをおすすめします。専門家は、あなたの状況に合わせて、適切なアドバイスやサポートを提供してくれます。安心できる相続手続きのために、専門家の力を借りることを検討してみてはいかがでしょうか。
地域別の相続手続きサポート情報
相続手続きを進める中で、相続人になれないケースがあることをご存知でしょうか? 例えば、故意に被相続人を死亡させたなど、一定の事由に該当する場合、その人物は相続人としての資格を失います。これを「相続人の欠格」と言います。
ただし、家庭裁判所の審判によって、一定の要件を満たせば、欠格者が相続人となることを認められる場合があります。これを「相続人の欠格宥恕」といいます。
手続きや必要書類は状況によって異なるため、お困りの際は専門家にご相談ください。
まとめ
相続人の欠格事由に該当する場合でも、家庭裁判所に申し立てることで相続権が回復する「相続人の欠格宥恕」について解説してきました。
相続は感情的な問題も絡みやすく、複雑になりがちです。専門知識が必要となる場面も多いので、弁護士等の専門家に相談することをおすすめします。状況に応じて適切な対応をとるようにしましょう。
おすすめコラムはこちら
県外でのマイホーム購入を目指す。夢の実現へのステップガイド|お役立ちコラム|東京中古一戸建てナビ (chukokodate.com)
中古住宅100万の真実|お役立ちコラム|東京中古一戸建てナビ (chukokodate.com)
中古住宅はどこで買う?選び方と注意点を徹底解説【初心者必見】|お役立ちコラム|東京中古一戸建てナビ (chukokodate.com)
宅地建物取引士 刈田 知彰(かりた ともあき)
中古住宅売買の専門家。不動産業界16年のキャリアを持ち、新築マンション販売から中古戸建て・リノベーション専門へ転向。「買ってからがスタート」をモットーに、構造・耐震・断熱など建物の本質を見極めた住まい選びをサポートしています。
その他読んで頂きたい関連コラム
会員様限定の『非公開不動産』を閲覧したい!
カンタン無料会員登録で、一般には公開されていない物件情報をご覧いただけます。
今すぐ無料会員登録
お電話でのお問い合わせ:0120-246-991