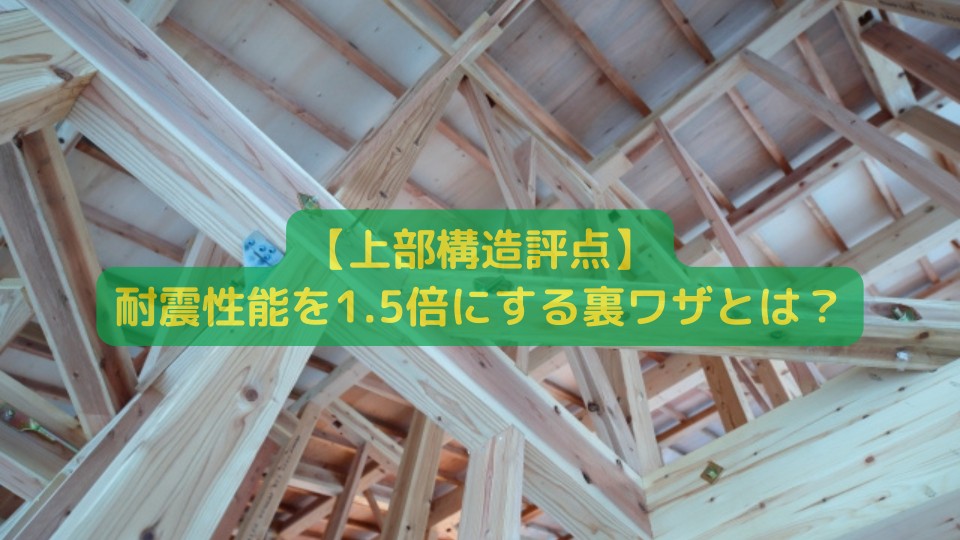
「家の耐震性を高めたいけど、具体的にどうすればいいんだろう…」
地震の多い日本で暮らす私たちにとって、住まいの耐震性はとても重要なテーマです。この記事では、建物の耐震性を示す指標「上部構造評点」に着目し、その評点を引き上げて安全性を高めるための具体的な方法を分かりやすく解説します。
この記事で分かること
-
上部構造評点の基本的な考え方
-
耐震性を高めるための具体的な改修工事
-
専門家が推奨する実践的なアプローチ
この記事を読めば、ご自宅の耐震性を向上させるための具体的なステップが分かり、大切な家族と住まいを地震から守るための知識が身につきます。
上部構造とは、建物の基礎よりも上の部分全体(柱、梁、壁、屋根など)を指します。この上部構造が、地震の揺れから建物を守る主役となるため、中古住宅などを選ぶ際には、その状態を確認することが非常に重要です。
築年数が経過した建物では、上部構造が劣化している可能性もあるため、購入前には専門家による耐震診断を受けることをお勧めします。
上部構造評点(Iw値とも呼ばれます)は、建物の耐震性能を数値で示した重要な指標です。この数値が高いほど、地震に強い建物であることを意味します。
震度6強の地震に耐えるのが基準
この評点は、震度6強程度の大地震に対して、建物が倒壊・崩壊しないかどうかを判断する基準として用いられます。
なぜ「評点1.5以上」が推奨されるのか?
建築基準法で定められた最低限の基準は評点1.0ですが、これは「一度の大きな地震で即座に倒壊はしない」というレベルです。しかし、繰り返す余震や、想定を超える揺れに見舞われる可能性を考えると、より高い安全性を確保することが望ましいです。
そのため、専門家の間では、より安心して暮らせる目安として評点1.5以上が推奨されています。評点を1.0から1.5に上げることは、耐震性能を1.5倍に高めることを意味します。最終的にどこまでの安全性を求めるかは家主の判断となりますが、家族の安全を第一に考えるなら、1.5という数値を一つの目標とすると良いでしょう。
評点は、主に以下の4つの要素を総合的に評価して算出されます。
-
建物の重さ 重い建物ほど、地震の際に大きく揺れる力が働きます。特に、重い瓦屋根などは評点を下げる一因となります。
-
壁の構造と量 地震の水平な揺れに抵抗する「耐力壁」が、十分な量、かつバランス良く配置されているかが重要です。
-
地盤や地形 軟弱な地盤や傾斜地に建てられた建物は、地震の揺れが増幅されやすいため、評価が厳しくなることがあります。
-
基礎工事の状態 上部構造を支える基礎にひび割れがあったり、無筋コンクリートであったりすると、耐震性は大きく低下します。
評点を高めるためには、以下のような耐震補強工事が有効です。
-
基礎の補強・改修 ひび割れの補修や、鉄筋コンクリートで基礎を一体化させる「増し打ち」などを行います。
-
接合部の補強 柱と梁、筋交いなどの接合部分に専用の金物を設置し、地震の揺れで抜けたり外れたりしないように強化します。
-
屋根の軽量化 重い瓦屋根を、軽量な金属屋根(ガルバリウム鋼板など)に葺き替えます。建物の重心が低くなり、揺れを軽減する効果が非常に高い工事です。
-
壁の補強 耐力壁が不足している場所に、構造用合板を張ったり筋交いを入れたりして、壁の強度を高めます。
耐震改修には費用がかかりますが、多くの自治体で補助金制度が設けられています。まずは耐震診断を受け、その結果に基づいて工事計画を立て、自治体の窓口に相談してみましょう。
一般的な流れ
-
自治体に相談し、耐震診断の補助金を申請
-
専門家による耐震診断を受ける
-
診断結果に基づき、改修計画を作成
-
耐震改修工事の補助金を申請
-
工事の実施
補助金の他にも、税金の控除や低金利の融資制度などが利用できる場合もあります。お住まいの地域の制度を積極的に活用しましょう。
Q. 上部構造評点と耐震等級の違いは?
A. 上部構造評点は、主に既存の建物(特に旧耐震基準の建物)の耐震性を評価する際に使われる指標です。一方、耐震等級は、新築住宅の性能を示すための基準で、等級1〜3で表されます。上部構造評点1.0が耐震等級1に相当します。
Q. 評点が1.0未満の場合はどうすればいい?
A. 震度6強の地震で倒壊するリスクがあるため、早急な耐震補強工事を検討してください。まずは専門家に相談し、どこをどのように補強すれば効果的か、診断してもらうことが重要です。
今回は、建物の耐震性を示す「上部構造評点」について解説しました。
-
上部構造評点は、震度6強の地震に対する建物の強さを示す指標。
-
最低基準は1.0だが、より安全な暮らしのためには1.5以上を目指すのが理想。
-
評点を高めるには、屋根の軽量化や壁・基礎の補強などが有効。
-
工事の際は、自治体の補助金制度を賢く活用できる。
適切な知識を持ち、必要な対策を講じることで、地震への不安は大きく軽減できます。この記事が、あなたの住まいの安全性を高めるための一助となれば幸いです。
おすすめコラムはこちら
シンクの下がカビ臭い悩みを解決!カビの原因と簡単対策法|お役立ちコラム|東京中古一戸建てナビ
国土交通省 2025年4月施行予定 4号特例制度縮小 ~2025年建築基準法改正によるリフォームへの影響~|お役立ちコラム|東京中古一戸建てナビ
東京で理想のリノベーション物件を見つける!穴場エリアとは?|お役立ちコラム|東京中古一戸建てナビ
著者情報
宅地建物取引士 刈田 知彰
(かりた ともあき)
ハイウィル株式会社では主に中古一戸建てや新築一戸建て住宅の仲介をさせて頂いております。刈田です。
私が不動産業界に飛び込んでから早18年が過ぎました。最初に入社した会社は新築マンション・新築戸建ての企画・開発・販売までを行う会社でした。そこで新築マンションや新築戸建てのノウハウを学び営業してきました。当時の私は何の考えもなしに、中古は「保証もないし」「リスクが高い」と中古住宅のデメリットのみを説明する営業ばかりをしてきました。あるとき自分の間違えを受け入れ、これからの日本は新築住宅が脚光を浴びるのではなく中古流通×性能向上リノベーションが日本の住宅市場のスタンダードになっていくと確信し、現在は大正八年創業のハイウィル株式会社で皆様の中古住宅の購入そして性能向上リノベーションをワンストップで行えるサービスの手助けをメインに物件のご紹介をさせて頂いております。とはいえ今はその狭間の時代となり、新築住宅も中古住宅どちらにも需要があり、マンションも含めて多角的な物件をご紹介させて頂いております。
特に新築戸建てから中古戸建てのことならなんでもご相談ください!
また、ハイウイル株式会社は築古戸建て住宅のリノベーションを得意としている会社になります。是非「増改築.com」もご覧ください。

「性能向上リノベーション」をこれからされる方は「増改築.com」へ
増改築.comでは買ってはいけない中古住宅と買っていい中古住宅とは?|戸建フルリフォームなら増改築.com® (zoukaichiku.com)を解説しております。